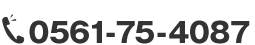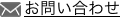こちらは、ミルガード(Milgard)製引き違いサッシ用のロック・クレセント。
引き違いだけでなく、上げ下げ窓(シングルハングやダブルハング)にも使われたりしますね。
このタイプのロック金物は、多くの輸入サッシで採用されていますが、似たような形でも微妙に違うというものがたくさん存在します。
ですから、形だけでなく、全体の大きさや取付け穴の位置や間隔、ストッパーの有無などといったことをチェックしないと、調達したはいいが取付けが出来なかったなんてこともあります。
今回のお客様にも既存のものの写真を送って頂いて、それと同じ形状・同じ大きさのものを調達しました。
このロック金物は、鋳物で出来ていますから結構丈夫なんですが、建具同士の噛み合わせが固かったりすると、回転する爪が削れたり、レバーが抜けてきたりします。
ロックがスムースに行かないようなら、長く気持ちよく使い続ける為に、取付け調整をしておきたいものですね。
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。
窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。
※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。