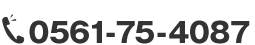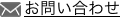昨日、名古屋市のお客様から、玄関に取り付けたスウェドア(Swedoor)の屋外側の木が劣化してきたので交換したいというご相談を頂きました。
このドアの表面には、少し厚みのあるチーク材が化粧板として張ってあるのですが、19年の雨風に曝されてドアの下の方が線状に剥がれてきています。
新築してから特に何もメンテナンスをしてこなかったということですから、自然素材のドアとしてはよく耐えた方だと思います。
木が剥がれた部分については、元に戻すということは出来ません。ただ、表面の汚れを紙ヤスリ等で擦り落として、パラペイントの屋外用木部防水塗料 ティンバーケアを塗ってこれ以上の劣化を抑えることは可能です。
そこで、お客様にどういったご希望かを確認させて頂いた処、これからはメンテナンスをしっかりするつもりなので、新しいドアに交換する方向で考えたいとのことでした。
鍵のシリンダーにもグラつきがあるようですから、心機一転して新しいスウェドアで気持ちよく暮らして頂くのもいいかも知れません。勿論、新しいドアにもティンバーケアを2度塗りしますから、5年くらいは塗り直しもしなくてよくなるはずですし、塗れば塗るほど塗装も強化されます。
勿論、水性塗料ですから、素人でも塗りやすく塗りムラも出来ません。玄関に木製ドアを取り付けている輸入住宅であれば、10年に一度は塗装や金物のメンテナンスをしてあげると、いつまでもお使い頂けるようになりますよ。
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。
窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。
※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。