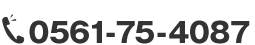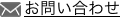愛知県のお客様の輸入住宅にお邪魔して、輸入の玄関ドア用ハンドルセットを交換してきました。
ハンドルセットは、クイックセット(Kwikset)製のホーソン。
古くなって、室内側のドアレバーが下がったままの状態になってきたのと、キーを1本どこかで落としてきてしまったということで、ハンドルセットごと交換することになりました。
キーをなくしただけのことであれば、新しいクイックセットのシリンダーはキーの鍵山をメモリーしているのを解除することが出来ますから、新しいキーの鍵山を覚え込ませれば、古いキーが使えなくなります。
これは、スマートキーと呼ばれる仕組みなんですが、これを利用すればダブルロックの2つの鍵を同一キーで開け閉め出来るようにもなります。
ただ、今回はレバーのバネもヘタってきたということですので、ハンドル自体も新しいものにしたいということになりました。
古いものも新しいもののアンティーク・ニッケルと呼ばれる色なんですが、古いハンドルは随分錆びてしまい、金属の光沢が殆どなくなっています。
まあ、これはこれで味があると言えばそうなんですが、金属で出来た機械ものですから、それなりに部品の錆びや劣化は生じます。

新しいハンドルは見ての通り黒っぽい銀色で、ニスを塗ったように光っているのが分かります。
勿論これも、20年もすれば錆びて時代が付いてくるのでしょうが、長く変化を楽しめるのが輸入住宅のいい所ですよね。
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、家全般のチェックやアドバイスを受けたいので、現地調査を希望するという方はお問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。
窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。
※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。ご使用になりたい場合は、事前にその旨ご相談下さい。