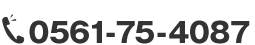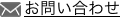敷地の狭い日本ですから、少しでも開放的な居住空間とすべく、2階の床をなくして吹き抜けにするのは、よくある手法です。
ただ、デザイナーや建築家の多くは、玄関ホールなどの然程広くないスペースを吹き抜けにすることはありますが、リビングのような大きな部屋を吹き抜けにすることには、躊躇するのかも知れません。
リビング全体を吹き抜けにするということは、それだけ2階のスペースが少なくなるということですから、2階の部屋が取りづらくなるのです。
先程も述べたように、狭い敷地に家を建てるということは、建ぺい率や容積率から考えても出来るだけ目いっぱいスペースを活用したいと思うのは人情です。でも、そうした考えが、プランを画一化したものにして、どこにでもありそうな間取りになってしまう原因だとも思います。
限られた敷地に如何に広々と感じさせる空間が作れるか、それが建築デザイナーの腕の見せ所ではないでしょうか。因みに、写真の吹き抜けは、半田市で建てさせて頂いたレンガ積み輸入住宅 K邸のリビングです。少し洋館っぽいですか?
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、私と話をしたいという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。