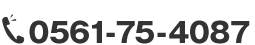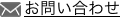先日、知り合いの輸入建材屋さんが、私共の会社に営業をしにいらした。
いろいろと新しい取扱いを始めていらっしゃるようですが、その中で紹介頂いたのが、ドイツの高性能木製サッシ、クネアズード フェンスター。どうでしょう、この分厚い木製のフレームと建具。パインの無垢材の寄せ木で出来ていますが、この重厚感は素敵です。
下地に防腐処理が施してあるらしいので、耐久性もある程度見込めますが、湿気や台風の多い日本では、防水塗装や窓の上に庇を付けてあげるという気遣いが必要かも知れません。
また、ダブルでLow-Eをコーティングしたトリプルガラスを使用。ガラスは4mm厚で、間の空気層は16mm。ですから、一番外のガラスから一番内側のガラスまでは、合せて44mmもあるんです。普通のペアガラスなら、17mm程度しかありませんからガラスもすごいですね。
さて、この窓の断熱性能を熱貫流率(U値)で表すことが出来ますが、何と「0.90w/m2・k」。更にパッシブハウス仕様にすると「0.70w/m2・k」。レベルが低い普通の国産アルミサッシでは、到底太刀打ち出来ないくらいの性能です。因みに、私たちが北米から調達しているトリプルガラスの高性能な輸入樹脂サッシですら、最高で「1.07w/m2・k」なんです。
さすがに、ベンツやポルシェを作る国、ドイツです。ただ、その分お値段もポルシェ級。性能にこだわりたいという方は、是非ご相談下さい。尚、このサッシは、写真のように内側に開きます。面白いですねぇ。
<関連記事>: これからのサッシは、ダブル断熱・トリプルガラスが主流か? (2012年12月9日)
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。