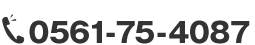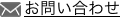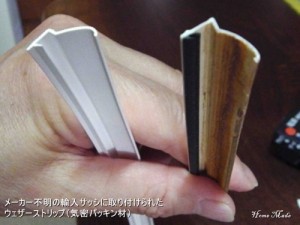こちらは、私たちがお客様の家具を購入しているアメリカの家具屋さんで販売されているイス。
マイクロ・ファイバーの布地で出来ているイスですから、肌触りもなかなかいい感じに見えますね。
親指と小指が肘掛けになっていて、野球のボールを握らせたら面白いかも知れません。(まあ、そんな大きなボールがあればの話ですが・・・)
クラシックにデザインされた輸入住宅には合わないでしょうが、モダン系のインテリアや子供部屋、自分だけの書斎なんかに置いたら、そこだけ趣向が変わっていい感じではないでしょうか。
こういう遊び心が欧米の人たちにはありますが、日本人も家づくりに是非取り入れてもらいたい感覚です。勿論、こうしたものばかりで構成されたインテリアだと落ち着かないと思いますから、アクセントとして使うべきだとは思いますが・・・。
数に限りがあるようですから、売り切れご免ではありますが、そんなに高いお値段ではありませんよ。お気に召した方は、家づくりを含めてご相談下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。