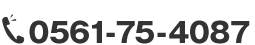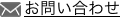以前から細かなメンテナンスや小屋作りなどをお手伝いさせて頂いてきた日進市の輸入住宅 T邸。
このおうちも新築した時の工務店は既になく、維持・補修については、私たち ホームメイドを信頼してお付き合いして頂いております。ほんと、有り難い限りです。
お付き合いをさせて頂いていた当初から気になっていたのが、屋根のカラーベスト・コロニアルの褪色・劣化。北側面の屋根などは、茶色く苔むしたような感じでしたから、早めにメンテナンスをして頂くようにお願いしておりました。
お客様にもいろいろご事情があって、それから随分月日が経ちましたが、ようやく外装のメンテナンスをやって頂けるというお話になりました。いや~、ほんとよく決断して頂きました!
この機会を逃してあと何年も後にやるとなると、塗り替えでなく、もしかしたら屋根材ごと葺き替えになるやも知れません。本当なら、2回目の塗り替えのタイミングと言ってもいいくらい時間が経っていますからね。
そう、このおうちの外装のメンテナンスは、新築以来初めてなんです。
外壁が、カナダの特殊なスライス・ブリック(レンガ・タイル)張りで、窓周り以外ほとんど劣化が見られないということが、反って補修のタイミングを遅らせてしまったのかも知れません。
ですから、今回補修メンテナンスをする箇所は、屋根だけでなく樋や軒の修理・塗り替え、バルコニーの防水やウッドデッキの作り替え、洗面水栓やカウンターの改装と多岐に亘ります。でも、ここでちゃんと直しておいたら、きっとこれからも素敵な輸入住宅を長くお使い頂けるはずです。
少しお金は掛かりますが、しっかり丁寧に直して次の世代につなげられるおうちにしていきましょうね。これから輸入住宅を建てられる方、今後メンテナンスを必要とされる方、仕事に気遣いの出来るビルダーとのご縁をどうぞ大切にしていって下さい。
新築をご計画の方や輸入住宅のメンテナンスでお困りの方は、お問い合わせ下さい。窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。