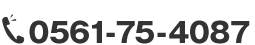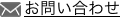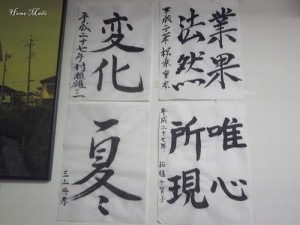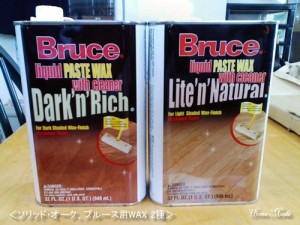日本の住宅に占める空き家の割合が、過去最高の13.5%に上昇したらしい。その数は、2013年10月時点で820万戸になったとのこと。
そんな家余り状態の中でも、新築の着工棟数は100万戸程度。ただ、昨今の消費増税や景気の低迷、所得の伸び悩みを受けて、今後は60万戸程度まで落ち込むだろうと言われているが、空き家が増える現状からすれば、それでも多いという気がする。
大手の住宅デベロッパーや住宅メーカーが、新しい分譲住宅や分譲マンションを大量に提供し、それを消費者が購入するという図式だが、古い住宅・マンションは全くと言っていい程売れていない。
日本の住宅の寿命は、26年前後と言われているが、それは長くメンテナンスして使い続けられる程の品質やデザインを住宅メーカーが提供してこなかったという側面があるからだろう。
また、低い品質や10年でトレンドが変わる場当たり的なデザインは、今新築される住宅でも変わっていない。これでは、古い住宅が売れずに放置されて、廃屋化していく現状は、将来も全く変わらないと言わざるを得ない。
いわば、日本の住宅は、一世代限りでゴミと化す消費財であり、メンテナンスして何世代も住み続けていこうと思えるだけのポテンシャルを持っていない。ネガティブな意見で申し訳ないが、1000万円もしない金額で家が建つなんていう日本の住宅には、実質メンテナンスする価値がないかも知れないのだ。
でも、新築で手持ちの所得を費やし、30年後にはその住宅が空き家になり、最後には廃棄されるというシステムを続けていけば、日本の資産はどんどん目減りしてしまい、そのうち国の借金である国債の総額をも下回ってくるだろう。そうなれば、近い将来日本経済が破綻することにもなりかねない。
私たちは、普遍的な美しいデザインと、より耐久性のある高品質な自然素材で家づくりをすべきではないだろうか。そういう価値あるものを後世に残していきたいと、次の世代の人たちにも思って頂けるような住宅こそが、生き残っていくはずである。
その為に、レンガ積みの外壁や美しいドライウォールの内装を私たちは提案・啓蒙していかなければならないし、財産となる本物の輸入住宅を長くメンテナンスしていくようなビルダーとならねばならないと感じています。
消費者であるお客様の意識、施工者であるビルダーの意識、その両方が変わらなければいけない時期がやってきています。でなければ、空き家率が30%という20年後は乗り越えられません。価値のない住宅が淘汰・解体される時代は、そこまで来ています。
欧米のように美しい古い街並みが維持される日本を作りましょう!こうした私たちの考えや建築に共感され、輸入住宅の新築・メンテナンスをご計画の方は、ご相談下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。