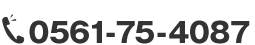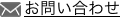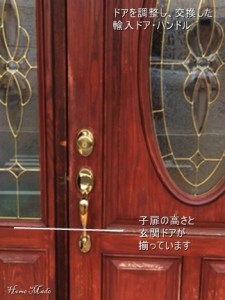今日は、一般的な住宅会社の土台伏せの模様を書かせて頂きます。
土台とは、立ち上がり基礎の上に載せる角材を言います。最近は、コンクリートの基礎の上に床下の通気を促す目的や直接土台を載せた時に起きる結露を防止する為に、基礎パッキンを間に入れる工法が取られています。
こうすることで、シロアリが好むジメジメした床下環境を作らない工夫をしているのです。
基礎パッキンは、黒い樹脂製のように見えますが、その材質の殆どは石の粉(炭酸カルシウム)で出来ているので、建物荷重による圧縮変形や経年劣化が殆どないという特徴を持っています。
そして、写真の土台は、他社の現場で施工されたダッカーウッド。防腐防蟻剤(オレンジ色の薬剤)が加圧注入されたダッカーウッドの土台には、木の芯(中心)から外れた柔らかい辺材を使用しています。
また薬剤を染み込ませる為に、表面にクサビ形の傷がたくさん付けられているのが分かりますか。
材種は、恐らくベイマツではないでしょうか。ベイマツにはシロアリのような虫が嫌がる匂いはありませんから、薬剤でのシロアリ対策をするしかありません。(メーカーによっては、更に柔らかいベイツガを使ったり、若い間伐材を寄せ木にした集成材を使うところもあります)
そして、高温で加圧注入の処理を行った木材は、強度的に少し脆くなっているような気がします。
逆に、私たちが土台に使う木は、ヒノキやヒバの芯(心)持ち材。ヒノキやヒバは、あのいい香りの元となるヒノキチオールという物質を含んでいますから、他の樹種よりシロアリは好まないと言われています。
芯とは木の堅い中心部分ですから、シロアリが比較的食べやすい柔らかな辺材よりも食害のリスクが少し下がります。但し、食べるものがなければ、シロアリは何でも食べるので油断は禁物。
私たちは、こうした工夫やベタ基礎などにして、出来るだけシロアリが侵入したがらない状況を作っているに過ぎません。それも、環境や人体に有害な防蟻処理剤などを使用しないで、自然の素材や摂理によってシロアリの侵入を防ぎ、こうした虫とも共存していく方策を選択しています。
自然の生態系に於いては、シロアリも大切な役者の一人です。だから、建物に被害が及ばない限りは、私たちがシロアリ駆除用の防蟻処理剤を使うことはありません。これは、シックハウス・アレルギー対策としても有効です。
こうした私たちの考えや建築に共感し施工を希望される方は、ご相談下さい。
<関連記事>: ホームメイドが使う土台の木は? (2013年3月20日)
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。