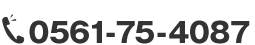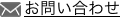先日大阪でアイエムエス・カナダ製ボレアル・サッシのコイルバランサーの交換を行ってきたという記事を書かせて頂きました。
今回は、同じコイルバランサーでも菊竹産業製シュエット・サッシに使われているバランサーの交換のご依頼を頂きました。
それは、愛知県岡崎市にある輸入住宅の浴室サッシなんですが、写真のようにバランサー・コイルが千切れてハウジングから外れてしまいました。
本来は、ハウジングと呼ばれる樹脂製の箱の中に巻かれているゼンマイ式のバネなんですが、長年曝された浴室の水分や湿気によって弱くなってしまったということも考えられます。
バランサー・コイルはステンレス製ですから、水分で劣化するということは起こらないはずですが、少しでも成分が異なる金属が混じっていれば、それが亀裂を生じさせたということは十分あり得ます。何れにしても、またフレームを広げる特殊な道具を使って、窓のフレーム内に入っているバランサーを引っ張り出して交換しなければなりません。
サッシ・フレームを傷付けないで元通りに戻すのは、この方法かヒートガンで塩ビ・フレームを曲げるしかありませんから、特殊工具はこの作業の要とも言えます。Chouetteのサッシのメンテナンスで長く困っていらっしゃる皆さん、バランサーを交換すれば新築時のように開閉が可能となりますから、諦めないで相談して下さいね。
<関連記事>: 樹脂フレームを傷めないコイルバランサーの交換 (2019年1月31日)
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、私と話をしたいという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。
窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。また、これらの記事が、多くの皆さんのお役に立てれば幸いです。
※ 「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容や価格が更新されている場合があります。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。